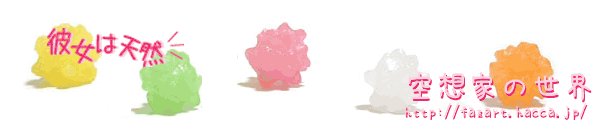
Index>Novel>彼女は天然>
彼女の手料理
「お疲れでしたー」
俺のバイト先は喫茶店だ。
12月24日、クリスマスイブ。町中が浮かれ騒ぐこんな日にバイトしている理由なんて明白だ。
――何の予定もない、ってな。
そんなことを思いながらバイト先を出ると、心の底から身が冷えた。
くそー。何で世の中クリスマスなんだ、間違ってる。
コートの襟を立てて、肩を震わせる。昼はそこまででもないが、さすがに夜中は冷え込む。
バイト先は図書館の真ん前で、図書館の敷地内を突っ切って近道をすれば家まで15分くらい。
寒いので自然と早足になる。
冬の空気は冷えてピンと張りつめている。風がないのは救いだろう。これで風が吹いていた日にはさらなる寒さを体験できただろうからな。
空にはきれいな満月が浮かんでいる。
世間の恋人どもはきっと「あの月に乾杯」なんぞとくさいことでも言い合ってるんだろう。
ねたましい。
手がかじかんでしまう前にアパートの明かりが見えてきて、俺はさらに足を早めた。家に入って、こたつに入って、ケーキの代わりにミカンでも食おう。
郵便受けを覗いて、舌打ちしながらダイレクトメールとチラシを取り出す。せめてラブレターの一通でも入っていればいいのになんて、あり得ないことを考えながら体を反転させて階段を見て、凍り付いた。
あり得ない人影がそこにある。
「……あー」
どう切り出していいもんだか、迷う。
「何でこんな日にそんなところにいるんだよお前」
我ながら冷たい物言いだと思う。
だが彼女持ちで万年春な男がそこにいたらそう言いたくもなるだろう。
「そろそろ諦めて帰ろうかと思ってたところだ」
「ほー? こんな日にこんな所にいていいのかよ。クリスマスパーティはどうした?」
「……なんでだろうなあ?」
どうしようもなく困った顔で首をかしげられたって困る。
クリスマスの夜に、アパートの階段に男が待っていたところで、心が躍るわけがない。
それでも追い返すのは忍びなくて、横をすり抜けて階段を昇る。
手招きした気配を感じ取って、後ろからヤツはひっついてきた。
「ご近所で妙な噂になったらどうするよ?」
「俺とお前が? ありえねぇ」
お前が今日ここに来る自体がありえねえ、という一言は何とか飲み込んだ。
須賀祐介とは小学校からの縁だ。小中と一緒に学び、高校で別れて、大学でまた再会した。
祐介には幼なじみがいて昔から仲がよかったが、高校時代のいつからか何となく付き合う感じになっているらしい。
家族ぐるみのつきあいだから、今日は二家族でクリスマスパーティだ、とか言ってなかったか?
祐介の疲れた表情に引っかかりを覚えて、あえて突っ込まずに階段を昇った一番奥の扉のノブに鍵を突っ込む。
がちゃりと扉を押し開いて、上がり込む。
祐介も慣れたように鍵を閉めてついてきた。
奥の間に入るように促して、手前にあるせまっくるしい台所の小さなコンロにヤカンを乗せる。
熱い茶の一杯でも出すのが礼儀ってもんだろう。バイト先から帰ってきた俺だって充分寒かったんだ。動きもせずに座り込んでいたらしい祐介は冷え切ってるだろう。
急須と湯飲みを持って奥に向かうと、こたつの電源を勝手に入れて祐介はちゃっかり暖をとっている。
その正面に座って、湯飲みに茶を注ぐ。
「ほれよ」
「悪いなー」
二人して、黙り込んで熱い玄米茶をすすった。
俺から話を切り出すのもためらわれて、余計に沈黙が続く。
空気が重い。何だって俺はまた、ただでさえ予定もなく憂鬱なクリスマスに自室で男と面と向かって茶をすすってるんだろうか。
贅沢は言わない。
店はファーストフードでもいい。せめて女の子と過ごしたい、ってのは夢見すぎなんだろうか?
そっとため息をついていると、祐介がはっと顔を上げた。
「いや、悪いな、突然」
「どうせ予定もなかったからいいんだが」
「だろうと思った」
お前俺に喧嘩売ってんのか。
俺が険悪に目を細めたのを見て、慌てて祐介は手を振った。
「お前そういうちゃらちゃらしたイベントには興味なさそうだしな」
「そうでもないぞ?」
「そうは見えないんだろうな。空もお前はぱっと見近寄りにくいって言ってたしな」
「そんな遠慮するガラじゃないだろ、矢島は」
矢島空、というのが祐介の幼なじみにして彼女の名前だ。俺にとってもやっぱり祐介と同じように小中一緒で、大学で再会した間柄。
大体再会したときからして「あーっ! しんごくんだー!」とか言いながらタックルしてきたような女だぞ。
近寄りにくいも何もないだろう、それは。
「空は空だからなー」
分かるような分からないような祐介の言葉に、俺も納得したんだかしてないんだかよく分からないような気分になって、湯飲みに茶をつぎ足す。
彼女の名前を出した途端に苦い顔になった祐介をそれとなく観察しながら茶をすする。
祐介と矢島は、仲がいい。うらやましいかどうかは微妙だが。
その関係を端的に表現するのなら、兄妹のような間柄というのが正しいように思う。
矢島のノリと言動をやさしく見守る祐介の姿にはある意味尊敬を覚える。少なくとも俺には無理だ。
矢島は確かに可愛いが、一緒にいると疲れる。
祐介が疲れたように見えるのもそれだろうか? クリスマスに彼女との――というか家族ぐるみらしいが――約束を蹴ってこんな所にいるなんて、とうとう長い春が終わったんだろうか。
沈黙はさっきよりもよほど重く感じられた。間が持たなくて、ミカンに手を伸ばした瞬間祐介が息を吐いた。
思わず手を止める。
「なあ、新吾。ちょっと聞いてもらっていいか?」
「おう?」
ミカンに伸ばした手をそろそろと戻す。
真剣な眼差しの祐介の言葉を、ミカンを食いながら聞くのも失礼だろう。
「手料理が食べたいって言った俺が間違ってたのかな」
「……は?」
「言ったろ? ここ数年俺と空の家は合同でクリスマスを祝うって」
「ああ。若い二人が暴走しないように親も工夫しようってアレじゃないか? 公認なのはいいが、苦労するなお前も」
「いやー、暴走のしようもないけどなー」
「相手が矢島だもんな。それで手料理?」
自宅でパーティなら、それも有りだろう。そう思った直後に考えを改める。
「……矢島の手料理ッ?」
「そこで何で大げさに驚くんだよ」
祐介は明らかにむっとした。
「だって、矢島だぞ? 塩のかわりに砂糖、醤油の代わりにソースを使いそうじゃないか」
「お前の空のイメージって……」
「どこまでも限りなく天然」
「空はそこが可愛いんだよ」
「――のろけに来たのか? だったら追い出すぞおい」
恋は盲目って言うけど、そこまで矢島に夢中な祐介がわからない。一緒にいて退屈はしないだろうが……相手が、矢島だもんなあ。
あのよくわからない思考回路と一生付き合っていくつもりらしい祐介はある意味勇者だ。この先長い人生を矢島と。
信じられん。人生考え直せと忠告したい。
「のろけじゃない」
「百歩譲ってそれは認めてやろう。で、手料理を食べたいって言ったらどうしたんだ?」
俺は興味深く祐介を観察した。
矢島は料理が得意そうじゃないから、とんでもない物が出てきたのか?
だが相手は矢島だ。
その思考回路はミステリー。ふと気付くととんでもないことを言い出す女・矢島空。
その矢島がごく普通に焦げ焦げ料理をどーんと出して「砂糖と塩間違えちゃった〜」なんて言うとは思えない。
何かやらかしたんだろう。その結果に祐介がここにいるのは疑いようがない。
「パーティをキャンセルされた」
「よっぽど料理に自信がなかったのか」
そう言いながら俺はどこかで残念に思った。
矢島にしてはあまり面白くない選択だ。
「それなら手料理は諦めればよかっただろ」
「そう言おうと思ったんだけどな……」
両手で湯飲みをもてあそびながら祐介はため息を漏らした。
「その前に出かけてた」
「逃げるほど嫌だったのか」
問うと、祐介は絶望的な表情で首を横に振る。
「空はそんな後ろ向きなことはしない。いつでも前向きだ」
「前向きなのか……?」
「どこに行ったのかと思って近所を捜してたら、紙袋を抱えた空が帰ってきた」
「ほー、料理修行だな」
きっと食材でも買い込んだんだろう。すぐにうまく作る自信がないから、予定はキャンセルして寝ずに料理とか作りそうだ。
そう思う俺に表情を変えずに祐介は再び首を振る。
「空の思考はなんて言うのか、人とは違った方に向いてる」
「……まあ、独特だな」
うなずいて、祐介はささやくように呟いた。
「手料理が食べたいって聞いて、何で栄養学の本とか買ってくるのかな……」
「えいようがく?」
「普通、料理の作り方とか、そういう本買ってくるだろ……?」
その前に母親に聞きながら作るっていう手もありそうだけどな。
疲れたような祐介は「栄養学の本」に引っかかってるらしい。
「さすが矢島、やることがひと味違うな」
「健康のために栄養バランスを考えなきゃ、って俺はただ単に手料理が食べたかっただけで……なぜ栄養バランス」
「……なんでだろうな」
口では言いながら、何というかこれは結局婉曲なのろけなんじゃないかと俺は思った。
健康のために栄養バランス、って「将来ずっと私が貴方の食事を作るわ」とかなんとかそういうノリじゃないのか?
違うのか?
俺の穿った見方か?
「うまくなくてもいいんだ、俺のために頑張って料理してくれるとかいう事実がうれしいわけで、決して栄養学を学べなんて俺は言ってないぞ?」
「……お前帰れ」
馬鹿らしくなって、俺は祐介の手から湯飲みを奪った。
「とっとと帰れ。いいじゃないか、栄養学。お前のことを心底思ってるんだろう矢島は?」
「そうかねえ……」
「間違いなくそうだろうが。独り身男に延々とのろけるんじゃねえ。帰れ。矢島の好きそうなケーキでも買って帰ったら、パーティをキャンセルした事なんて忘れて参加するだろ」
「……新吾、お前一体空のことをどんな風に思ってるんだよ……」
呆れたように言いながら、それでも帰る気が出たのか祐介は立ち上がる。
「四丁目の角のクリーミーブランのブッシュドノエルがうまいって評判だ」
「しかも何でそんな情報に詳しいんだお前」
「バイト先で聞いた。今日は9時までやってるって話だ――あと20分、ぎりぎりだな。がんばれ」
「おう」
うなずいて、祐介はひらりと手を振った。
「いきなり愚痴って悪かったな。じゃ」
去り際はあっさりしたもので、扉が閉まると階段を勢いよく下りる気配が伝わってくる。
俺はため息をついて、再びこたつに舞い戻った。改めてミカンに手を伸ばして、もう一度息を吐く。
なんで俺はクリスマスに婉曲なのろけを聞いた挙げ句に励ましてアドバイスなんぞしているんだ、まったく。
2004.12.14 up
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件などには、いっさい関係ありません。
感想がありましたらご利用下さい。