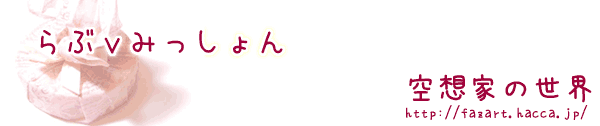
Index>Novel>
1.
店内は柔らかな木調で統一されていて、照明はクリームがかって見える。
十時半。
モーニングには遅くて、ランチにはまだ早い。
だから、店は混んでなくてすぐ入れたわけだけど。
見渡す店内にはお客さんもまばらで、私たちは入って窓際の角のテーブルに陣取ることができた。
ドリンクバーとサラダバーで、五百円。
飲み物をまずとって、サラダを皿に山盛りに盛って向かい合う。
「ふー」
私の幼なじみ――綾は満足げに息を吐いて、にこっと笑った。
「まあ食べてよ、ゆい」
「いただきます」
彼女の勧めにしたがって、私は両手を合わせる。
――そう、これは綾のおごりなのだ。
休みだし、ごろごろすごそうかと思っていたら数十メートル先から綾がやってきて、私を外に連れ出しやってきたのがこの店。
おごるからとにっこり笑って手早く注文もして好きに取ってきた飲み物とサラダに、私をここまで連れてきた綾の方は手を出すそぶりがない。
不思議に思いながら私は遠慮せずにサラダに手を出した。レタスに水菜にキャベツにトマト。かけたのは中華ドレッシング。
あとで他のドレッシングにも挑戦しよう――コーンとかも食べたいし。
綾はじいっと私を見ているだけだ。
「――私の顔に何かついてる?」
違うだろうなあと思いながら聞いてみると、綾はふるふる首を振った。
綾はかわいらしい子だ。小柄で、何というかちんまりしている。明るい笑顔がよく似合う。
美人というと嘘になるけど、かわいいと言ったら否定する人はいない、そういう子。
だから首を振る仕草もとてもかわいらしい。
ただし見た目だけは、だけど。
「……なにか、ある?」
おごろうって言うんだから、きっと何かあるんだろう。
何もないなら家で普通に遊んでいけばいいはずだ。半分確信を込めて聞くと綾はこくりとうなずいた。
「ちょっとね、お願いがあってさ」
「――なに?」
ちょっとだけ、身構える。
綾はかわいらしいけど、見た目以外はかわいいとは言い切れない。
だから何が飛び出してくるんだと、目を見返した。綾は真剣な眼差しで私の視線を受け止める。
「あのね、お菓子作りたいんだけど」
「ええ――?」
我ながら素っ頓狂な声が出たと思う。
「何か悪いものでも食べたッ?」
思わず張り上げた声に綾は不機嫌に顔をゆがめる。
「失礼だわー」
眉を寄せて彼女がようやく口に運んだ飲み物はブラックコーヒー。
砂糖はおろかミルクさえ入っていない苦い飲み物――綾は甘いものが得意じゃないんだ。
それがお菓子作りって、明日槍でも降ってくるんじゃないだろーか。
「でもどうしたのいきなりお菓子なんて」
「……何でソレを聞くかなぁ」
綾は苦笑して、肩をすくめた。
コーヒーカップをテーブルに戻して、そのまま右手の人差し指をぴっと私の前に突き出す。
「今日は何日?」
「2月13日」
何をまた突然聞くんだろう。
「明日は?」
「えーと……14日……」
っていうと。
「バレンタインデー……?」
導き出された答えは少なくとも私にとって信じられないものだ。
でも綾はそれにうなずいた。
「女の子でしょ、ゆい。一大イベント忘れちゃだめよ」
「そうは言っても私には縁ないしなぁ」
というか綾にだってあまり縁がないイベントのはずだ。
彼氏だっていないし、好きな人の存在も聞いたことがない。ついでに甘いのも嫌いだから、チョコレートが世間にあふれていても去年まではどこ吹く風だった。
私はといえばバレンタイン自体には縁がないものの、時期が終わってから値下がりしたのを何種類か買い込むくらいにチョコは好き――ってそうじゃなく。
「誰に渡すの? というか好きな人いたの?」
フォークを握りしめたまま、身を乗り出す。
私の鼻先をちょんと指でつついて、綾は顔をそらした。
「えーとまあ、そゆことになるね」
恥ずかしいから黙ってた、ってことか。
「でも、別に手作りやお菓子にこだわらなくていいんじゃない?」
「でも手作りだとうれしいって、タケちゃんが!」
「歌手の言うことまともに取らなくてもいいと思うけど。まさかそのタケちゃんに送るとかじゃないよね?」
だいたい芸能人に送ったところで本当に食べてもらえるかも怪しいし、手作りって言うのは敬遠されそうな気がする。
「まさかっ」
綾は驚いたような顔で否定した。
「私タケちゃんは好きだけど、そこまで入れ込んじゃないよ?」
「そーだよね」
ファンだって言う割にCDだって何枚も持っていない。全部買いそろえるのにお小遣いじゃ足りないって言うのももちろんだけど、綾の「好き」はどこか引いたようなところがある。
特に気に入ったのを何枚か買って、そこそこ好きなのをレンタルして。そうでもないのは「べつにどーでもいい」というくらい。
「――だったら誰にあげるの?」
興味を引かれて問いかけると、綾はにっと笑った。
「もちろん好きな人だよ」
「綾が義理チョコをばらまくほどマメとは思ってないし、それはわかってる。誰?」
「……田崎先輩」
「――だれ?」
聞き覚えがないので重ねて聞いた。綾はあきれた顔をする。
「わかりやすく言うと生徒会長」
「……え」
「何その反応」
「綾がああいう人を好きになるなんて意外で」
生徒会長を面と向かう機会なんて、滅多にない。私と綾が通う聖華学園は巨大とはいえないけど、そこそこ大きい。
その生徒の中のトップという位置づけの生徒会長は何かと人前に出る機会は多いけど、面と向かって話す機会なんてほとんどない。
「妙にかわいい人でねぇ」
「って親しいワケっ?」
綾は首を横に振った。
「文化祭の時に、委員やったでしょ。その時にさ」
「あー、そういえばがんばってたよね」
「ゆいも協力してくれたしね。あのときは助かったよ」
「でも文化祭なんて何ヶ月前の話よ。そのころから好きだったの?」
「うん、まぁ……」
歯切れ悪く綾はうなずく。食べるでもなく皿をつついて「うー」とうなった。
「なんというか、恥ずかしくて黙ってた。ごめん」
「何で謝るの?」
「なんとなく?」
それにしても生徒会長て言えばだ。1年の時から生徒会に入っているとかいう、しっかりとした物言いをする人じゃなかっただろうか。
妙にかわいいって。
「なんかかっこよくなかったっけ、生徒会長」
「見た目はねー。中身はかわいいよ」
綾は妙に力強く言い切って、自分でうんうんうなずく。
「そんなに親いんだ?」
「そこそこ仲良くしてもらったから。それで気になって」
「バレンタインを機会に告白と?」
「……そういうことになるかな」
「手作りお菓子にこだわらなくてもいいんじゃないかな」
呟いたのは、綾にお菓子づくりができるかなと思ったところが大きい。
綾の家庭科の成績を、残念ながら私はよく知っているから。
「甘いの苦手だしねー。それもちょっと思ったけど」
綾はようやくサラダを食べつつ、うーんとうなる。
「でも、手作りってポイント高いよって言われたし」
それはそれがおいしかったらの話なんじゃないかなあ、と思う。私が協力すると言ったって、全部作るわけにもいかないだろうし。
「会長さんだって、甘いの好きかどうかわからないじゃない。だったら甘いのが苦手な綾だからこそのものを贈った方がよくない?」
綾は驚いたように目をぱちくりした。
「違う?」
だめ押しで聞いてみると、綾は慌てたように首を振った。
「ところが向こうは甘いのが苦手じゃないらしいんだよね」
「……詳しいね」
「うん、情報源があって」
「その子に手作りの方がいいよとアドバイス受けたの?」
「そゆこと。クリスマスとか誕生日とかバレンタインとか、今までそんなイベントに縁がなかったらしいから、効果抜群だろうって」
「――あんなにかっこいいのに?」
私が生徒会長を一番近くで見たときは、文化祭の準備の時だった。各クラスに下見に来ていたらしく、ひょいと顔を覗かせたのだ。
確かあのとき、綾は「会長お疲れさまですー」とか言って一番に駆けつけたんだった。真面目に報告してるのかと思ったら、それだけじゃなかった、ってことだ。今更そんなことに気付く――好きなんだとかは思いもしなかった。
「情報によるとね。ほんとかうそかわからないけど、まあ今フリーなのは事実みたいよ」
「ひどいなあ」
いきなり声が聞こえたのはそのときだ。
聞こえた方に視線を向けると、若いお兄ちゃんが一人立っている。いつの間に近づいていたんだろう、話に夢中で気付かなかった。
「僕は嘘は言ってないよ」
私は驚いて綾を見た。綾も驚いたような顔をしていたけど、一瞬にして笑顔になる。
「人の心は見えないものだから、親友だからってほんとのところはわからないですよ?」
「まあね」
すると情報源はこのお兄ちゃんなのか。
思わずまじまじと見つめてしまう。生徒会長の親友と言うからには一コ上で、綾と知り合いってことは先輩なんだろう。私や綾よりはちょっと大人びているように見える。
「羽村先輩、わざわざありがとうございます」
「礼には及ばないよ」
立ち上がって言った綾に、先輩はにっこり笑う。
綾はわざわざ先輩まで呼んでいたんだ……後輩の相談に乗って、わざわざやってくるこの先輩はものすごくいい人なんじゃないだろうか。
でも、今からお菓子作るのに?
実はこの先輩はお菓子づくりが趣味とか?
私の視線に気付いたんだろう、先輩は笑顔のまま首を傾げる。私は慌てて目をそらして、なんでもないです、とアピールした。
「羽村先輩そっちどうぞ」
立ち上がったままの綾が私の隣を指したのにあわせて、再び先輩を見ると先輩の方は何とも言えない表情を浮かべてた。
「えーっと、失礼します」
「あ、どうぞ」
間抜けな挨拶を交わしてから先輩は私の隣に座り込む。綾もすとんと腰を落とした。
「ドリンクバーとサラダバー!」
メニューを持って近寄ってきたウェイトレスさんに綾は勢いよく注文を告げる。
「じゃあ、先に行こうかな」
先輩は言って私たちがさっき行ったドリンクとサラダのコーナーに向かう。その後ろ姿が充分離れたのを確認して、私は綾に顔を寄せた。
「あの先輩も、文化祭の委員だったの?」
「何言ってんの、副会長だよ」
「え」
呆れたような綾の声。私は眉間にしわが寄るのを感じた。副会長ってことは生徒会副会長ってことで――朝礼の時なんかの生徒会の様子を思い出す。
「うーん、制服じゃないしなあ」
生徒会選挙なんてずいぶん前だし、遠目に見たおぼろげな印象で思い出せそうにない。
「羽村雄太先輩」
名前を言われてもねえ。
「てか、それよりも副会長を味方に引き込んでるその方が不思議だわ」
「うひひ」
綾はかわいい顔にかわいらしくないにやーっとした笑みを浮かべた。
「ギブアンドテイクよ世の中」
「どんな条件だしたのよ」
「ひーみつー」
くすくす肩を揺らす綾はやけに楽しげだった。
「会長のことを教えた上にここまで来てくれるなんて、いい人ねえ」
「暇なんじゃない?」
そのいい人に綾はあっさりひどい評価を下した。
「好きな人の親友に言うことじゃないんじゃない?」
「でも暇なのは間違いない話と思わない?」
「……いいんだけどさあ」
私は空いたお皿を持って立ち上がる。
「おかわりいってくる」
「ほーい」
途中で先輩と会釈を交わしてすれ違って、レタスとキャベツとコーンとタマネギとトマトを山のように盛る。朝御飯はほとんど食べてないし、お昼も追加で食べたりはしないだろうから、晩御飯まで持つように食べておくに越したことはない。
迷った末に店のオリジナルドレッシング――すりりんごがポイントらしい――をかけて、席に戻る。
「おかえり」
「ただいまー」
私の帰還に気付いた先輩が通りやすいように席を立ってくれたので、さっきと同じように綾の目の前に戻ることができた。綾の隣の方が気が楽なんだけどな、というのは先輩に失礼だろう。
「前から好きだった割に、前日に動き出すなんてぎりぎりよねえ」
「うーん、ほんとは手作りでマフラーでも、とか思ったんだけどさあ」
「……それは」
無謀というか不可能じゃないんだろうか、と言ったら失礼な話かな。
文化祭当時から仮に作り始めたにしても、この時期に作り上げるのは無理だろうし何より編み目が恐ろしい代物になっているはずだ。
「諦めた。やっぱり向いてないわ、間に合いそうにないし」
「だよね」
思わず力一杯うなずいてしまう。
「それならお菓子の方がまだすぐできるかなと」
「そこまで手作りにこだわらなくていいと思うけど」
「手作りの方がポイント高いみたいなんだもん」
私はつい先輩を横目で見てしまった。その視線に何か感じたのか、居心地悪げに身じろぎする。
「だめ?」
綾は何かを訴えかける目で私を見上げる。それに否を唱えることは私にはできなかった。
「会長の健康を損ねちゃいけないから、協力はするけど」
「ひどいこというなあ」
「あり得ない話じゃないと思うわ。それで何渡すの?」
一口に手作りといってもいろいろある。定番はやっぱりチョコレートだろうか。
「えっと、一応本は買ったんだけど」
綾は鞄から大判の本を取りだした。
ハートのチョコの写真がメインの、かわいらしいお菓子の本だ。
「どれがいいかな。甘いの嫌いだし予想もつかない」
テーブルに本を載せてぱらぱらとめくる。
「どれもおいしそうだね」
「そう?」
甘いものが得意じゃない綾には私の思いが伝わらなかったらしい。
「トリュフとかどうかな」
「丸めるのが無理じゃないかな」
綾は作り方のところをじーっと見て、それからこくこくうなずく。
「発狂して投げ捨てそう――生チョコとかは?」
「それならまだよさそうかなあ……あ、冷蔵庫で一晩冷やし固めるって、それって失敗したとき再チャレンジできない」
「ぬーん」
「フォンダン・ショコラって言うのは?」
先輩が写真を指し示した。
「食べたこと無いものにチャレンジする勇気が足りないです」
成功したかしていないか判断できないし。
「ハート型に溶かして固めるって簡単そうじゃない?」
「どうせならもっとこだわろうよ」
「なんかゆいが真剣だー」
「この子はすごいと思わせるようなすてきなのつくろうよどうせなら」
「それは、海は喜ぶだろうけど……」
「ど?」
先輩は私と綾を交互に見て、曖昧に笑う。
「あれじゃないかな、背伸びしすぎるのもどうかと」
「綾にお菓子を手作りさせようと思わせた原因の人に言われたくないです」
「笹原さんが甘いのやお菓子づくりがそこまで苦手だと思わなかったから」
綾は可愛らしく見えるから、よけいそこは誤解されるんだよね。
「どうせらしくないですよーだ」
「そこを頑張って作る、っていうのはポイント高いと思うよ。海にも言っておく」
「いえす、がんばるっ」
先輩のフォローに綾はすぐさま復活して、男らしく拳を握りしめた。それはかわいくない。
「ゆい、何がいいと思う?」
「なにがいいかなー」
三人で再び本をのぞき込む。
「先輩はお菓子づくりが趣味なんですか?」
「へ?」
私がさっきの疑問を口にすると、先輩はびっくりしたようだった。
「ぜんぜん。なんで?」
「わざわざ休みの日につきあってくれるなんて、お得意なのかと」
「いやいや、暇だし」
「毒味役できてもらったんです、ねー?」
「……毒て」
綾の言葉にさすがに嫌そうな顔で先輩が呟く。
「会長の味覚もよくご存知ですか」
「そこそこはね」
「甘いのはどれくらい得意なんですか、生徒会長は」
「ケーキまでは大丈夫じゃないかな」
「よし」
呟いて、綾から本を奪い取る。ぱらぱらとめくって、私は目的のページを二人に示した。
「これでいこう、ガトーショコラ。おいしいよね」
綾は首を傾げながら「おー」と言い、先輩はゆっくりうなずいた。
2005.02.12 up
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件などには、いっさい関係ありません。
感想がありましたらご利用下さい。